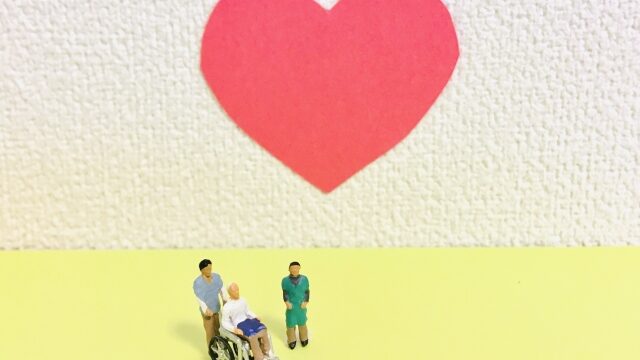親が高齢になってくると、相続のことも気になり始めますよね。
「うちは相続するような財産はないよ」と思っているかもしれませんが、親が家を持っている場合は、相続が発生します。
2024年4月より、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、3年以内に登記をしなければなりません。
我が家は夫が実家を相続することになり、一昨年(2023年)、相続登記を行いました。
その際、司法書士など専門家に依頼せず、自分たちで相続登記を行いました。
今回は、その時のことを書いていきたいと思います。
夫が実家を相続することになった
夫の父(義父)が亡くなったのは2年前。
それまで夫の父母が住んでいた実家を、夫が相続することになりました。
義父が亡くなっても、義母がまだ実家に住んでいたので、本来なら義母が相続するのがいいのかもしれません。
しかし、義母が相続しても、何年かでまた相続になってしまう。
それなら、子供が相続した方がいいのではということになりました。
夫には妹がいます。
当初、夫は「地元に住んでいる妹が相続したほうがいい」と言っていました。
そして、義妹が相続について調べ始めたようなのですが・・・。
ある時、義父の葬儀やお墓のことで義妹と意見が合わないことがあり、それまでいろいろな手続きを任せきりにされていた義妹がキレて、義妹は相続放棄をしました。
相続する実家は、築60年の木造、ニコイチ(2軒連棟)の住宅。土地は借地です。
正直言って、価値はほぼありません。
もっと価値がある住宅ならば、義妹も相続したのではないでしょうか。
こうして、夫が実家を相続することになりました。

自分たちで相続登記をした理由
相続した夫の実家は、建物のみで、築年数もかなり経っていたため、価値はほぼありません。課税評価額で行くと、「55万円」です。
相続登記は司法書士など専門家に依頼すればやってもらえます。
司法書士に依頼する相場は8~10万前後だそうです。
この実家に10万円か。
葬儀などにも費用がかかったのに、またこんなにもお金がかかるのかぁ~!きびしいな。
正直、私はそう思いました。
昔なら登記をしないでおくというのもあったのかもしれません。
でも、翌年の2024年からは相続登記は義務化になる。
それならやっておくべきなのでしょう。
そこで、専門家じゃないとできないのかと調べてみると、自分でもやってもよく、しかも、なんとかできそうです。
そのころ、私は、仕事をしていなかったので時間の余裕もあったため、相続登記を自分たちというか、主に私がやることにしました。

私が行った相続登記の流れ
相続登記は申請書類を作成し、必要書類を添付して申請をすることで登記ができます。
私が行った登記までの流れを簡単に書いてみます。
①登記内容を確認する
申請書類を作る前に、まずは、実家の登記事項証明書(登記簿)をとります。
現在の登記の内容を確認するためです。
登記事項証明書は管轄の法務局に行けば取れますが、オンラインでも申請することができます。
私は夫の実家が遠方で、管轄の法務局も遠いので、オンラインで申請して取りました。
②申請書類を作る
申請書類は、法務局のホームページなどでテンプレートがあるのでそれを使いました。
検索すれば、たくさんテンプレートや記載例が出てくるので、それほど難しくありません。
③遺産分割協議書を作る
必要資料の中に、遺産分割協議書というものがあります。
遺産の分割について、相続人全員で協議して決めた結果を記載したものです。
遺言書があれば、これは不要なようですが、遺言書がなければ相続人全員が署名捺印した「遺産分割協議書」が必要になります。
これも、テンプレートと記載例がネットでたくさん出ているのでそれを活用しました。
今回の法定相続人は、義母(配偶者)、夫(子)、義妹(子)ですが、義妹は相続放棄の手続きをしたため、相続人から外れます。(その代わりに相続放棄の手続きをした書類を添付)
義母と夫で協議した結果、夫が単独で実家の不動産を相続するという内容の遺産分割協議書を作成しました。

④添付資料を集める
そのほか、戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、印鑑登録証明書などの書類が必要となってきます。
故人(被相続人)と相続人全員の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票が必要になってきます。
市役所などで取れますが、これを集めるのが地味にめんどくさく、時間がかかります。
特にめんどくさいのが故人の戸籍です。
故人の戸籍は、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要になります。
戸籍が結婚や転籍などで本籍地が移って、違う市町村になっていると、それぞれに申請しなければなりません。
でも、親の戸籍がどう移動しているかなんて、知らないですよね。
しかも、生まれた時からの戸籍となると、ますますどうなっているのかなんてわかりません。
だから、戸籍を取ってみたら、本籍地が移動していて、前の本籍地がある市町村に申請をするというのを何度か繰り返すことになります。
しかも、遠方の市町村なので、郵送で依頼をするのですが、支払いが郵便小為替だったりします。(中には、カード払いができるとこもありましたが)
これが地味に面倒で、間が開いてしまったりして、必要書類がそろうまでにちょっと時間がかかってしまいました。
ただ、ここで「他に子供がいた!」とか相続人が増えたりとかしなかったので良かったです。
知り合いは、調べたら知らない姉弟がいたという話をしていましたから。
⑤登録免許税分の収入印紙を用意
相続登記の際には登録免許税を払う必要があります。
収入印紙で払えるため、登録免許税分の収入印紙を用意しました。
なお、登録免許税の計算は下記のとおりです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
今回の場合は、評価額55万円だったので、55万円×0.4%=2200円でした。
⑥登記申請書類を提出する
郵送で提出できたので、郵送で提出しました。
原本等が返ってくるので、返信用封筒もつけました。
提出後、少し書類に不備があったようで、法務局から連絡がありました。
その時に、たまたま夫の地元に行く用事があり、管轄の法務局に出向いて、説明を受けて、その場で修正をして申請をして無事登記が行われました。
そんなこんなで、何カ月もかかって、申請書を作り、資料を集めて、登記は完了しました。
自分で申請してみて思ったこと
相続登記は、資料集めは面倒ですが、申請にかかる事務処理は思ったほどは難しいものではありませんでした。
それは、今回、相続した不動産が建物1つだけだったことと、相続についてもめることがなかったからです。
不動産の数が多かったり、複雑な内容だと素人には難しいかもしれません。
また、私は、昔、都市開発の仕事をしていて、登記関連の業務を少しだけ担当したことがあります。
業務で相続登記はもちろんしたことないのですが、それでも、登記関連の業務の経験があったため、登記の事務について「難しそう」といった先入観がありませんでした。
その分、他の人よりも、相続登記の事務処理がやりやすかったかもしれません。

今回、我が家は、自分たちで相続登記をしました。
申請の事務処理自体は思ったほど難しくなかったといっても、面倒であったことには変わりありません。
相続する不動産にお金をかけたくなくて、時間の余裕があるなら、自分でやるのも良いと思います。私たちは自分たちで行って、コストを抑えることができました。
ただ、資金的な余裕があるなら、司法書士など専門家に依頼した方がラクだし、確実です。
特に複雑な内容であれば、専門家に依頼するのが安心です。
すでに、相続登記は義務化は始まっています。
自分でやるにしても、専門家に依頼するにしても、早めに取り掛かるのが良いと思います。
今回は、私の相続登記を自分で行った体験を書きました。
申請してから月日が経っているため、書いた内容は、正確でない部分もあると思います。
なので実際に登記申請を行う際は、きちんと調べてくださいね。
なお、法務局が、相続登記の申請の仕方について詳しく書いてあるハンドブックを用意してくれています。
相続登記をする方は、ぜひ、こちらを参考にしてみてください。
相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック):法務局